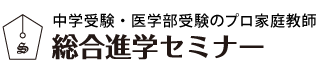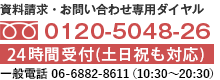中学受験をするしないに関わらず、毎日の学習習慣は小学校低学年のうちに身につけておくべきだと言われています。どのようにしたらいいのか、上手な学習習慣の身につけ方をごご紹介いたします。
CONTENTS:
1.学習習慣は何年生から?

毎日学習する習慣は、なるべく早くから身につけるに越したことはありません。可能であれば小学校に入学してすぐにでもといいたいところですが、まだ学校という環境に不慣れな状況ですので、あまり無理もさせられません。
中学受験を考えていない子どもはもちろんのこと、受験を考えている子どもであっても、低学年のうちは受験など現実味を帯びないでしょう。学校でそれなりに勉強をして帰ってきて、また勉強しなければならないのかという気持ちになるのも理解できます。
しかし、学年が上がるにつれ、学習内容は難しくなりますし、宿題も多くなるので、嫌でも机に向かわなければならないようになります。それならば、なるべく早くから勉強を習慣化させたほうがスムーズです。
小学1年生のうちは、無理のない範囲で少しずつ学校の予習復習程度から始め、2年生から本格的に学習を習慣化できるようになればいいでしょう。
1年生のうちは国語も算数も導入的な要素が大きく、ご家庭で少しでも予習復習をすれば十分に理解できる学習内容です。
この時点で少しでも学習内容の先取りできていると、授業を楽しく受けることができ、本人にも「得意意識」が生まれます。これが後々とても重要です。
2年生になると、国語で習う漢字がぐっと増えますし、算数では「かけ算」を習います。「かけ算」でつまずくと、「算数ができない」「算数は苦手」というネガティブな意識が生涯ずっとつきまとうことになります。予習、復習、ドリルなどで毎日学習する習慣を身につけるのにはちょうどいい時期といえるでしょう。
2. 学習時間は日々どのくらい必要?

学年などにもよりますが、はじめは15~20分くらいから始めて、まずは1時間を目標にしてみましょう。
1時間はとうてい無理だという場合は、あまり無理やり強制的に1時間勉強させるよりも、15分でも20分でもいいので、とにかく毎日続けることが大事です。「継続は力なり」、最初から1時間と張り切りすぎて3日坊主で終わってしまうのが1番よくありません。必ず毎日一定時間机に向かうクセだけはつけるようにしましょう。
親からすると、小学校の授業時間は45分や50分と決まっていて、ほとんどの児童はきちんと座って授業を受けていますから、家でも20分や30分くらい問題がないように思います。しかし、家庭になると、20~30分でも毎日勉強するのはなかなか容易ではありません。
なぜ家庭ではたとえ20分でも勉強させるのが難しいのでしょうか。それは、家には誘惑するものがたくさんあるからです。少し手を伸ばせば漫画やテレビにスマホ、ゲームなどがないでしょうか。それらの誘惑にすべて勝たなければなりません。
学校では授業という遊びの誘惑のない場に監視している先生がいて、みんなが同じように椅子に座って学習していますので、1時間弱でも座っていられますが、いざ家で1人となると、子どもにとってはたいへん難しいことになります。
ですから、たとえ家庭で1時間学習できなくても、「なんで1時間もできないの!」と怒るのではなく、20分でも15分でも毎日続けてできたら、「毎日ちゃんと勉強できてえらいね」「すごいことだよ」と褒めてあげましょう。低学年ほど、もっと褒められたいとよりがんばるようになるでしょう。
なるべく低学年のうちから、短くても机に向かい、学習する習慣を身につけ、勉強するということの抵抗感がなくなるようにしておくことが肝心です。そして、徐々に学習時間を増やし、毎日1時間は勉強することを目指すようにしましょう。
3.中学受験を考えていなくても学習習慣は必要?
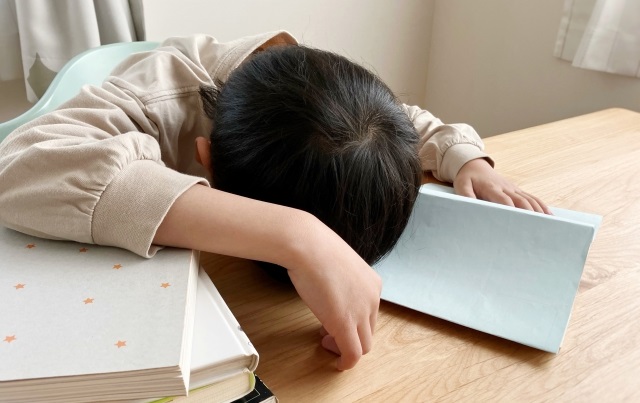
中学生になれば、私立でも公立でも毎学期ごとに中間テストと期末テストという定期試験があります。生徒たちはその定期試験に向けて勉強し、それらの成績によって高校受験や大学受験の方向性が決まります。
小学生の時に全く学習習慣がなかった人は、中学生になって定期試験を前に高い壁を感じることでしょう。試験に向けた勉強を1人でしたことがないので、どうしていいのかわからないからです。
小学校の授業中に受ける通常テストとはぜんぜん違います。どう勉強するのかわからないため、勉強せずに試験に臨み、当然のことながらいい結果にはなりません。
いい成績が取れないと、どんどん勉強がつまらなく嫌いになって、いわゆる負のスパイラルに陥ることになります。そうならないためにも、中学受験をするしないに関わらず、小学生の早いうちから日々の学習習慣を身に付けておくことがとても大事です。
ましてや中学受験を考えているのなら、通塾して学校の宿題に加えて塾の宿題もやらなければならなくなります。さらに、受験が近くなると通常授業の上に特訓授業や志望校対策の勉強も必要になって、家庭での学習は1時間どころではなくなります。
受験しない子どもは自ら学習習慣を作らないと、毎日しっかり勉強する受験組とどんどん差が開いて、勉強に苦手意識を持つようになります。そういう意味でも小学生の早いうちに学習習慣を身につけさせることが望ましいといえるでしょう。
4.家庭学習といっても何を勉強させればいいの?
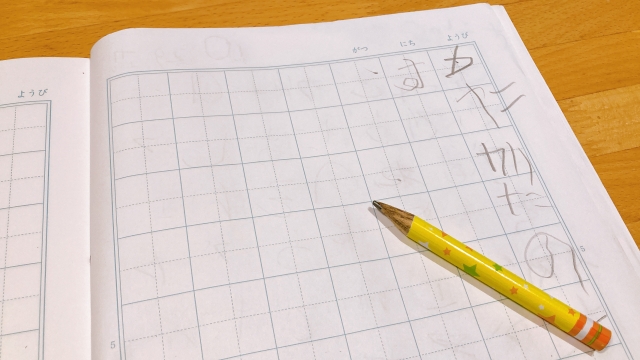
中学受験組なら塾の宿題が多いので、1時間などすぐに経ってしまいます。しかし、中学受験を考えていない場合、学校の宿題以外に何をすればいいのか迷うかもしれません。
学校の宿題は日によってあったりなかったり、すぐに終わるような宿題だったりします。
その日の宿題に合わせていたら、学習時間がまちまちになってしまい、なかなかしっかりとした学習習慣は身につきません。塾に通っていなくて、学校の宿題だけでは数分で終わってしまうというのであれば、市販の問題集を購入して学習するのもいいでしょう。
大事なことは、家庭内できちんと決められた時間机に向かって毎日勉強することで、習慣化させることです。この勉強をしなければならないというものはありませんが、できれば学校の授業で少し苦手だと思う教科と得意教科の2教科から始めるのがいいでしょう。
苦手教科は、遅れをとったりさらに状況を悪化させたりしないために、テコ入れする必要があります。しかし、苦手科目は子どもにとって面白いわけがないので、自分の得意とする教科もいっしょに進めていくことで学習意欲を高めることができます。
そうやって少しずつでも苦手科目に手をつけていくことで苦手意識が薄れ、興味を持つようになり、学習時間も必然的に増えていきます。
「何が得意で何が苦手かもわからない。何をしていいかわからない」という場合は、毎日算数の「計算問題」と国語の「漢字」だけでもやらせてみてください。市販のドリルや学校のドリルを繰り返しやらせるのもおすすめです。
前述の通り、苦手科目と得意科目で進めると継続しやすいので、算数は苦手だけど理科が好きなら算数と理科という組み合わせで勉強を進めてみましょう。
現状、学校の授業にはきちんとついていけていて、中学受験をするかしないか迷っている人や通塾するかどうか迷っている人なら、一度大手塾の公開テストや五ツ木駸々堂テストなど業社のテストを受けてみるといいでしょう。
どの教科で点が取れてどの教科で点が取れていないのかを客観的に把握してから学習内容を決めるのもいいかと思います。その場合も、前述と同じ理由で、できなかった教科だけでなく、よくできた教科もいっしょに勉強を進めていくようにしましょう。
5. 学習習慣はどうやれば身につく?上手な習慣化4つの方法
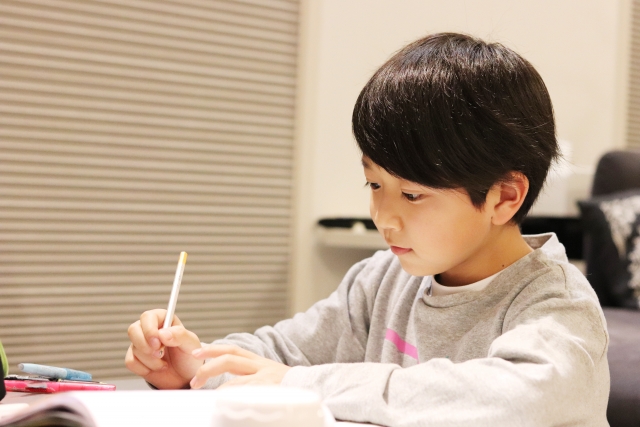
01. 一週間単位で計画を立てる
学習を毎日の習慣にさせるには、勉強時間をできるだけ毎日何時から何時と同じ時間にすることが望ましいのですが、習い事をしていたりして毎日同じ時間は難しいという場合も多いでしょう。
その場合、必ずしも同じ時間にしなければいけないわけではなく、毎日コンスタントに一定時間勉強するクセ(習慣)をつけることが大事です。習い事などを複数しているのであれば、〇曜日は何時から何時、〇曜日と週末は何時から何時と一週間の計画を立てておくのがいいでしょう。まずはそこからがスタートです。
02. 日常の行動と学習をセットにする
学習の習慣化をスムーズに行うために、よく言われているのは、何か日常の行動とセットで行うことです。
例えば、次のように考えます。
・ 朝起きて顔を洗って着替えたら、朝食までの〇分計算ドリルをやる
・ 朝食を食べたら学校に行くまでの〇分問題集をやる
・ 夕ご飯を食べてお風呂に入るまでの〇分復習と漢字を練習をする
・ お風呂から出たらテレビを観るまでの〇時まで、算数を勉強する
などといったように、日常の行為とセットにしてしまうことです。
その際に、できれば親がいっしょに付き合ってあげるとより効果的です。とくに低学年のうちは親がいっしょになって、勉強や宿題をみてあげてください。指導するのではなく、ドリルや問題集を添削してあげて、間違ったところを再度やり直しさせたり、いっしょに考えてあげたりしてください。
03. 親ができること~上手なサポートとは
大事なことは「できたところをしっかりと褒めてあげること」です。それが継続させる大きなポイントです。「こんな難しい計算できたんだ、すごいね」や「よくこんな難しい漢字知っていたね」「さすが生物博士だね」など、親から褒められると、子どもは嬉しくてまた明日もやりたいと思います。
最初はイヤイヤ始めた勉強も、少しずつできるようになって、学校でもテストでいい点が続くと、得意気に「このくらい余裕」などと言ってくるようになります。そのように言ってきたら「すごい!じゃあ、今度もうちょっと難しい問題やってみるか」とランクアップさせ、さらにモチベーションを上げることもできるでしょう。
04. 家庭学習の場所はどこがベスト?
学習場所は、自分の部屋でもリビングでも構いませんが、自分の部屋でやるのであれば、やはり親もついていてあげることをおすすめします。前述したように、漫画やゲームなどの誘惑に負けてしまう恐れがあるからです。「〇分まで勉強したら」または「〇頁まで学習したら」ゲームしてもいいと約束させ、学習時間はきっちり守らせるよう目を光らせておきましょう。
おすすめは、リビングでの勉強です。親も家事や仕事をしながら子どもの勉強を見守りやすいからです。当然ですが、その間は親もリビングでテレビやスマホを見たり、大声で楽しそうにおしゃべりしたりはしないようにしてくださいね。
6.まとめ~家庭学習の習慣化を全力でサポート

今回は中学受験をするしないに関係なく、小学校の低学年から学習習慣を身につけることの重要性とそのやり方についてご紹介しました。
低学年のうちに学習習慣を身につけておくことは、今後のとても大きなアドバンテージとなります。30分でも1時間でも毎日机に向かう習慣がついていれば、高学年、中学生、高校生になっても、スムーズに家庭学習を進めていくことができるはずです。
家庭学習の習慣化について、「なかなか自分たちだけでは難しい」、「どうすればいいのかよくわからない」など、何かしら不安があるようでしたら、ぜひ一度プロの家庭教師にご相談ください。本人の性格やご家庭の方針など、1人ひとりに合った最適な家庭学習を全力でサポート、ご指導いたします。

家庭学習をきっちりサポート!
学習の習慣化ならプロにお任せください!