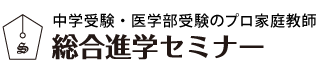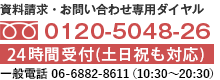最難関中学受験をさせるため、進学塾などに入塾するスタートが年々低年齢化しています。果たして幼児から通塾させる必要があるのか、疑問や不安に思う保護者は少なくありません。そこで、今回は幼児から家庭でできる「子どもの素地を育む4つのこと」をご紹介いたします。
CONTENTS:
1.最難関中学を受験するためには、幼児から学習させるべき?

一般には小学3、4年生から
一般に中学受験のために塾に通うなどして本格的な受験勉強を始めるのは、小学校4年生の春(小3の2月)からが多いといわれています。しかし、実際に最難関~難関校を目指すのならば、小学校3年生(小2の2月)や、もしくはそれ以前から入塾させるというご家庭もあります。
それでは、それまで何もしなくていいのかというと、疑問符がつきます。小3からのスタートを少しでもラクに始めさせてあげたいと思うのなら、やれることはできるだけ家庭内でやっておくに越したことはありません。
小学3年までに家庭でやっておくべきこと
まだ幼児のうちからあまり勉強でガツガツさせるのはかわいそうだし、逆に勉強嫌いになってしまったら困ると考える保護者も多いかと思います。
そこで、幼児や小学1~2年生の子どもが、いわゆる机に向かうような学習ではなく、家庭で無理のない程度にできる「素地を育む4つのこと」をご紹介します。
これらは、中学受験を終えた保護者が「子どもがもっと小さい時にやっておけばよかった」とよく口にするような内容です。将来的に最難関中学の受験を少しでもお考えのご家庭や、子どもの「素地を養いたい」方はぜひご一読ください。
2. 本好きの子どもに育てるには~音読の効果とは
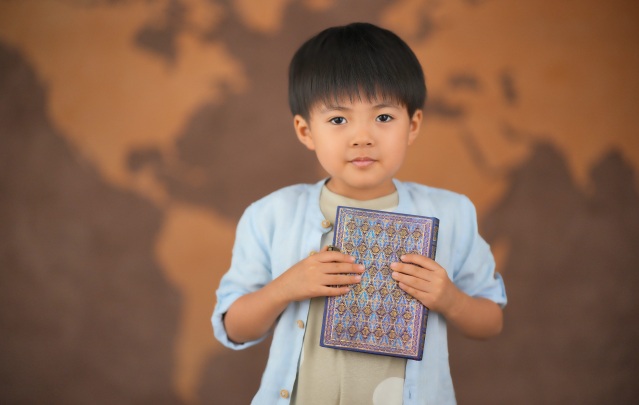
まずは絵本の読み聞かせから
子どもの「素地を育む」いちばんの近道でカンタンな方法は、「いかに本好きの子を育てるか」ということ。それには、なるべく乳幼児など小さいうちから絵本の読み聞かせをしてあげることです。
子どもが自らいきなり読書をするわけではないので、まずは親が可能な限りたくさんの絵本を小さいうちから読んであげましょう。そのうち本人がお気に入りとなる本が出てきて何度も「これ読んで」とせがむようになります。親は「またこれ?読むのも疲れる」と思うかもしれませんが、そこは我慢して何度も何度も繰り返し読んであげましょう。
月齢にあわせて少しずつ文字量を増やす
最初はほとんど文字のない絵本から始まり、月齢にあわせてじょじょに文字量を増やしていきます。読み聞かせをする際には、なるべくはっきりした声で抑揚をつけて読んであげましょう。
子どもは大好きなお父さんお母さんの声を聞きながら、本を読む楽しさを覚えます。そのうち自然と気に入った本を自ら手にとり読むようになります。こうして知らず知らずのうちに本好きの子どもになっていきます。
少なくとも幼児から毎日少しずつでも読み聞かせをしていると、小学校に入学するころには相当な語彙力を身につけているはずです。
音読のすすめ~なぜ音読がいいの?

小学校に入れば文字もしっかり読めるようになるので、本を読む際は音読させるとさらにいいでしょう。音読の効果はいろいろいわれていますが、漢字や語彙力の向上になるだけなく、脳の活性化や集中力、コミュニケーション力にも効果があるとされています。
また、口に出して読むことで、感情移入しやすくなり、文章の内容を理解しやすくなります。文章や構成を意識して読むので読解力を鍛えることにも繋がり、当然読書スピードも上がります。
さらに親の前で音読をすれば、読めない漢字を聞いたり、読み間違えをその場で訂正したりすることもできます。読む本は学校の国語の教科書でも構いません。いい予習にもなり、授業も面白く感じ、楽しみにすら感じるかもしれませんよ。
中学入試の問題は長文化の傾向
最近の難関中学校入試では、国語はもちろん、算数や理科、社会の試験でも、何千字もの文章を読ませる試験が増えています。決められた時間内にすべて解かなければならないので、読解力や速読力が結果に大きく影響することは間違いありません。
読書や音読をすることで子どもの素地を養い、中学受験だけでなく、その後の受験や就活にまでも大きな影響を与える可能性があります。なるべく小さいうちから習慣化できるといいでしょう。
上手に読めたら褒める!できなくても怒らない
大事なことは、上手に読めたら子どもを褒めることです。カードなどを作って、上手に読めたらスタンプやシールなどを貼ってあげたりするのもいいでしょう。たとえ読み間違えたとしても「前にも読んだじゃない」「なんで読めないの」などと叱責したりネガティブなことは決して言わないでください。
勉強として「読まされている」のではなく、あくまで自らが自分の意志で「読みたくて読む」という状況を作ってあげることが大切です。
3.算数脳を育むあそび

子どもの「素地」、とくに「算数脳」を育むのには、やはり幼いうちから「数字に慣れる」ことです。「数字」といっても、計算ドリルのような学習教材をやらせるという意味ではありません。
楽しく数をかぞえるようなあそびがおすすめです。ここではそんな「算数脳を育むあそび」をご紹介します。
身近に遊べるものとしては、「トランプ」などのカードゲームがおすすめです。「ババ抜き」や「7ならべ」「神経衰弱」などから始め、じょじょに「51」や「大富豪」などレベルアップしていきます。
その他、「UNO」のような数字や色を合わせるカードゲームでもいいでしょう。まずは楽しみながら数字に慣れることが大事です。
「すごろく」的なボードゲームにもいい効果があります。何マス進んだ、相手と何マス差がついた、あと何マスで「あがり」など、自然と数字の概念が定着します。
数がかぞえられるようになったら、サイコロを2個同時に使ってもいいでしょう。2個の出た目の数をかぞえさせることにより、遊びながら簡単な足し算もできるようになります。

おもちゃのお金を使った「お店屋さんごっこ」もおすすめです。最近はキャッシュレス化が進み、あまり現金を見なくなっているかもしれませんが、そんな時代だからこそ、あえておもちゃのお金で「買い物ごっこ」をしてみましょう。
おもちゃのお金がなければ、折り紙などで手作りしても構いません。1円玉、10円玉、穴を黒く塗った50円玉に100円玉と500円玉、1000円札などを作り、おままごとの野菜やケーキなどに、金額(価格)をつけて買い物ごっこをします。
子どもの月齢にあわせ、初めは値段設定も簡単にします。トマトやなすは10円。りんごは20円くらいの設定にして遊びます。買う物も1つだけにし、例えばトマトやなすは10円玉1枚で買えるけど、りんごなら1個20円なので、10円玉が2枚必要だということを遊びながら学習していきます。
本物のレジのように金額のところをバーコードで読み取る真似をし、「ピッ」といいながらお買い物するとたいへん喜びます。
慣れてきたら、金額も上げて物によってさまざまな値段にします。親子がそれぞれ500円ずつ持って、互いに買い物をします。楽しく遊びながらも1円が10枚で10円、10円が10枚で100円ということをだんだんと覚えていきます。
じょじょに内容を難しくしていき、複数の買い物をしたらいくらになるのか、またおつりはいくらになるのかなど、足し算や引き算を使うように高度にしていくといいでしょう。
※成長にあわせ、野菜などの価格をふだん利用するスーパーなどのリアル価格に設定すると、「この前は500円でこれだけ買えたのにいまはこれしか買えない」や「トマトは高くなったけど、レタスは安くなった」など、経済や社会学も学べるようになりますよ!

算数の育脳のひとつとして、「図形」感覚を養うものとして効果的なあそびが、「折り紙」や「積み木」「ブロック」などです。
折り紙をこう折ったらどのような形になるのか、どう折り目をつければこの形になるのか、一部を切って広げたらどんな形になるのかなど、実際に手を動かすことで自然に「平面図形」感覚が身につきます。
同様に、積み木やブロックあそびは「立体図形」感覚を養うことに適しています。積み木は何個まで上に高く積み上げることができるのか、ブロック10個でどんな形や積み方ができるのか、理想の形を作るにはどの形のブロックが何個必要かなど、無意識のうちに立体図形感覚が身についていきます。
幼児は放置していても夢中になって遊びますが、時々「わあ、ずいぶん高く積み上げたね、すごいね」や「これなあに?とってもすてきな形だね」などと関心を示し、褒めてあげるとさらに熱心に遊び、工夫もしますから、いい育脳になりますよ!
算数脳だけではない、アナログゲームの効果!
上記でご紹介した、いわゆるアナログゲームは、単に「算数脳」を育むだけではありません。スマホなどのデジタルゲームと違い、人と対面で接しますので、アピールしたり相手の表情を読み取ったりします。
また、デジタルゲームのように負けそうになったからといって、簡単リセットすることもできません。相手あってのことなので、たとえ負けが確定していても、そのゲームは最後まで参加し、次のゲームで挽回しようという気持ちになります。
つまり、アナログゲームで遊ぶことで、コミュニケーション力や忍耐力、持続力なども養えるのです。とくに幼児のうちにアナログゲームの魅力に触れさせておくことをおすすめします。
4.地図あそび

地図パズル
日本地図や世界地図のパズルなども、子どもの「素地」を育むあそびとしておすすめです。幼児は視覚による印象がとても大きいので、都道府県や世界の国々の形を合わせていくパズルなどがあれば、数か月で親よりも詳しくなったりします。
以前、「兵庫県の形は口をタコにしたお腹の出たおじさんみたい」といった未就学児がいました。子どもは見て思ったままの印象を記憶します。そして、その幼少期の記憶はしっかりと残ります。
中学入試でも、都道府県の形から答えを導き出すような問題が出たりすることがよくあります。小さいうちに楽しく遊びながら地図が覚えられるのなら、やっておいて損はないでしょう。
東大生の家には〇〇〇がある!?
以前テレビの番組で、家に「地球儀」あったという東大生が6割近くいることが紹介されていました。全国平均では3割弱なので、東大生はその倍も多く地球儀を持っていたことになります。恐らく平面地図も含めればさらに高い割合になるのではないでしょうか。
家に地球儀があれば、物心ついたころには自分は地球に住んでいて、それが球体であること、世界にはたくさんの国があることを無意識に理解するでしょう。
また、大リーグで大谷翔平選手が活躍したら、「アメリカってどこだろう」さらに、「ドジャースってアメリカのどこにあるのかな」や、サッカーの試合で相手国について、「ブラジルはどこ?」「スペインやフランスは?」などと親子で探すことができます。
「日本はここだから、ずいぶん遠いね」「ここにはどんな食べ物があるんだろうね」などと想像も会話も膨らんでいくでしょう。
決して学習というモードではなく、楽しく自然に興味をもつようにもっていくことが大切です。そのような意味でも日本地図や世界地図、地球儀などはインテリアやパズルあそびなどとして、リビングや子ども部屋など、いつも目につくところに飾っておくことをおすすめします。
5. 周辺環境の観察

身近な植物や生物を調べる
子どもの素地を育むのは家の中とは限りません。外出した際、ただ目的地まで歩くのではなく、周囲を観察しながら会話するようにします。
「あそこの赤いお花、とてもきれいで変わった形しているね」「曼殊沙華とか彼岸花っていうんだよ」や、「あ、この葉っぱ、色が変わってきているよ」「これは何の葉っぱだろうね」「みてみて、赤トンボだよ。この指止まらないかな」などと語りかけながら歩いてみましょう。
できれば家に帰ってから図鑑などで調べるといいでしょう。「この木どれだろうね」「葉っぱの形からすると、柿の木かな、それとも桜かな。どれだと思う?」などと話します。秋なら「どんぐり調べ」もおすすめです。拾ってきたどんぐりを図鑑などで調べたり、工作したりしてもいいでしょう。
それによって、子どもは自然とどの草花や樹木がいつ開花したり実をつけたりするのか学びますし、観察力もつきます。拾ってきた実や葉っぱで遊ぶのは小さな子どものほうがずっと上手で、その創造力には親のほうがびっくりさせられますよ。
影や空の観察
影や空の観察もとても有益です。昼間ならば、「お昼の12時なると、影がこっちに出るね」や、「夕方の影は昼間よりも長いよ。不思議だね」などと面白がってみせます。
また、雲を見て「あの雲の形面白いね」「あ、あれはソフトクリームみたいだよ」「あっちは猫さん、あれは何の形に似ているかな」などと話します。成長にあわせ、図鑑などで雲の名前を調べたり、「うろこ雲が出ているからもうすぐ雨かな」などと言ったりするようにするとよりいいですね。
夜ならば「お月さまずいぶん細いね。あのお月さまのことを”三日月“っていうんだよ」や「この前に見た時は三日月だったのに、お月さまがだいぶ大きくまんまるになっているね。もう満月なんだね」などと話します。
いずれも勉強と考えるではなく、他愛ない親子の会話として、親から楽しんで子どもと会話してあげてください。難しい話をする必要はありません。幼児期や小学校低学年時は、「影や月の形が時間や季節によって変わる」「いろいろな形の雲がある」ということだけでも知っておくといいでしょう。
調べ癖をつける

植物にしても空の観察にしても、わからないことはすぐに調べるというクセをつけましょう。それには「わからなかったら調べなさい」と子どもにいうのではなく、まずは親が率先して興味を持ち、楽しそうに調べることが大切です。
幼児のうちは、スマホやパソコンなではなく、できるだけ図鑑や辞書などの書籍で調べることをおすすめします。親がスマホばかり見ていると、当然子どももスマホばかり見るような子どもに育ちます。少なくとも子どもの前だけでも、親は本や辞書などで調べるようにしましょう。
その親の姿をみて、いつの間にか自然と子どもも自ら図鑑を見て調べるようになります。そこには学習しているという感覚はなく、面白いし楽しいから進んで学ぶようになります。
このようにして育った子どもは、いっしょに歩いていると、小さいうちからすぐに「みてみて、アリさんがいっぱいいるよ!」や「あっ、大きい雲、オバケみたい!」と大きな声で親に伝えようとしてくるでしょう。
子どものさまざまな反応に対し、決して無視をしたりうるさがったりせずに、「すごいね、よく見つけたね」「ほんとうだね。面白いね」と笑顔で応えてあげましょう。子どもはさらによく周囲を観察し、いろいろな発見をするでしょう。
6. 褒め上手な親になる
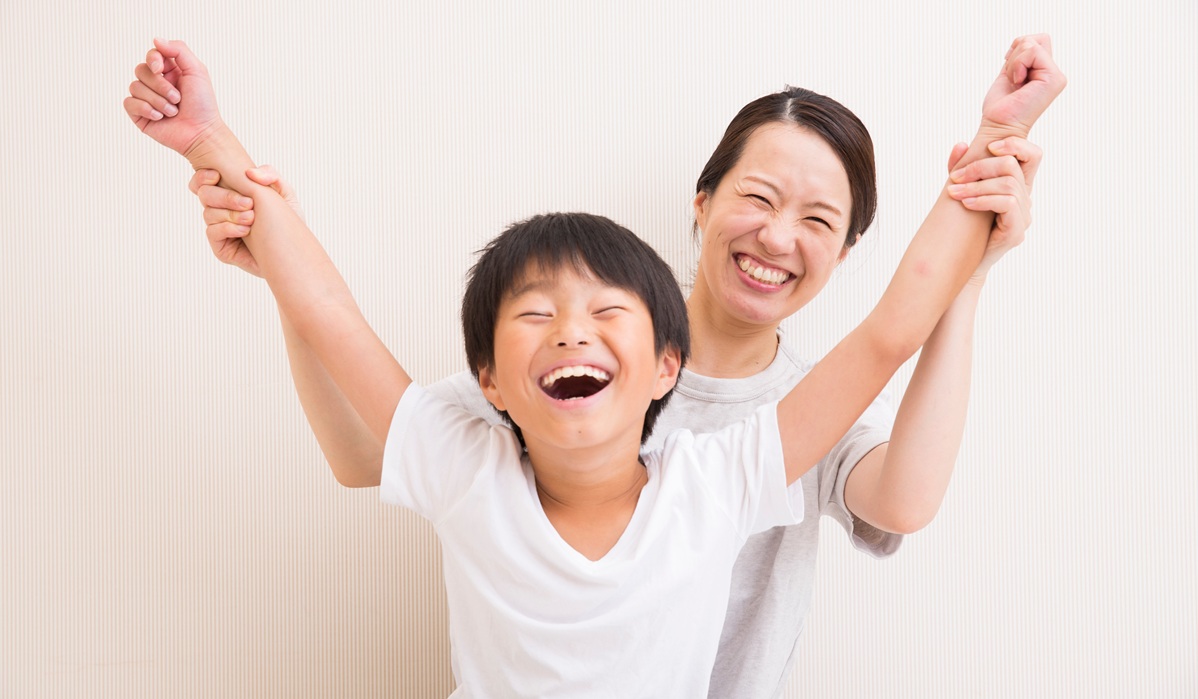
まずは褒めること
これまでご紹介した4つの「子どもの素地を育むこと」は、楽しく「あそび」として行っていれば自然と身についていくものですが、さらに効果的なのは、「親がいかに上手に褒められるか」です。
上手に音読ができたり、まだ習ってもいない漢字が読めたり、サイコロの足し算が速い、積み木やブロックを上手に積み上げる、身近に咲いている花の名前が言えた等々、何でもいいのです。大いに褒めてあげましょう。
幼稚園児や小学生の低学年の子どもで褒められて嫌がる子はいません。このくらいの年齢での学習に対するモチベーションは「親に褒められること」です。年齢を重ねた大人が、誰かに褒められたいから仕事などを頑張るというと、頑張る動機としてはやや幼稚に聞こえます。しかし、小さい子どもにとってみたら「親に褒められたいから頑張る」というのはとても立派な動機なのです。褒められると、「また何か見つけよう」や「もっと上手にやろう」などという気になり好循環が生まれます。親はまた子どもにそう思わせられるようにうまく促すことがカギになります。
上手に褒めるには?褒めすぎに注意!
ただし、なんでもかんでもやみくもに褒めればいいというわけではありません。不必要に褒めちぎっても子どもは見抜きますし、褒めても「またか」となり嬉しくもなくなり、「褒め効果」も出なくなります。
基本として、しかるべき時にきちんと褒められる「褒め上手な親になる」というスタンスが大切です。少し難しいかもしれませんが、単純に親が「よくできたな」や「よくがんばったな」「すごいな」などと思えれば、そこは大いに褒めてあげてくださいね。
7.まとめ~素地の効果と育み方

素地を育む効果とは?
今回は将来最難関中学受験をすることを見据えて、いかに幼児期から「素地を育む」かということに焦点をあて、「親子でできる4つのこと」をお伝えしました。
もちろん、まだ幼児のうちから中学受験を意識する必要はありません。もしかしたらスポーツや音楽、アートなどの才能が開花し、専門的に目指すようなことになるかもしれません。たとえそうなったとしても、これらの素地が必ずどこかでプラスに働くでしょう。
小学校3年、4年になって中学受験を考えるようになれば、進学塾などに通塾するようになり、やがて小5、小6と本格的な受験勉強に入っていきます。その時、この幼児期や小学校低学年時に身につけた「素地」が効果を発揮することになるでしょう。
まず親が楽しむことが大切!
これまでご紹介したことは、「素地を育むあそび」のほんの一部にすぎません。お絵描きや粘土あそびなど、他にもいいあそびはたくさんあります。年齢や子どもの性格、個性などにより、もっと他にも適したあそびがそれぞれあることと思います。
大事なことは、親子で楽しめる「あそび」であるということ。親は遊んでいるつもりが、「勉強を優位にさせるため」と力が入り、無意識に子どもに圧力をかけては本末転倒となります。
子どもが嫌がっていたら、それは楽しくもなくあそびでもありません。すぐにやり方を変えてください。うまくやる秘訣は、まず親が楽しむことです。親が楽しくなければ子どもも楽しめません。
これまでご紹介した4つのことをすべて行う必要もありませんし、親自身が興味のあること、得意なことから始めましょう。あるいはそうでなくても、一から勉強するつもりでいっしょに楽しく遊んでください。きっといい効果がたくさんありますよ!
ノーベル化学賞受賞者、北村進教授の子どもたちへの名言
最後に先日ノーベル化学賞を受賞した、京都大学高等研究院の北村進特別教授の名言をご紹介します。子どもたちへのメッセージを問われ、北村教授が尊敬するフランスの細菌学者ルイ・パスツールの言葉を引用されました。
|
“ Chance favors the prepared mind” 「幸運は準備された心のみに宿る」
|
※将来の中学受験や家庭学習について、何かしら不安があるようでしたら、
ぜひ一度プロの家庭教師にご相談ください。
本人の性格やご家庭の方針など、1人ひとりに合った
最適な家庭学習カリキュラムを全力でサポート、ご指導いたします。

家庭学習をきっちりサポート!
最難関中学受験ならお任せください!