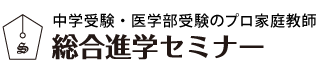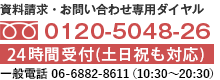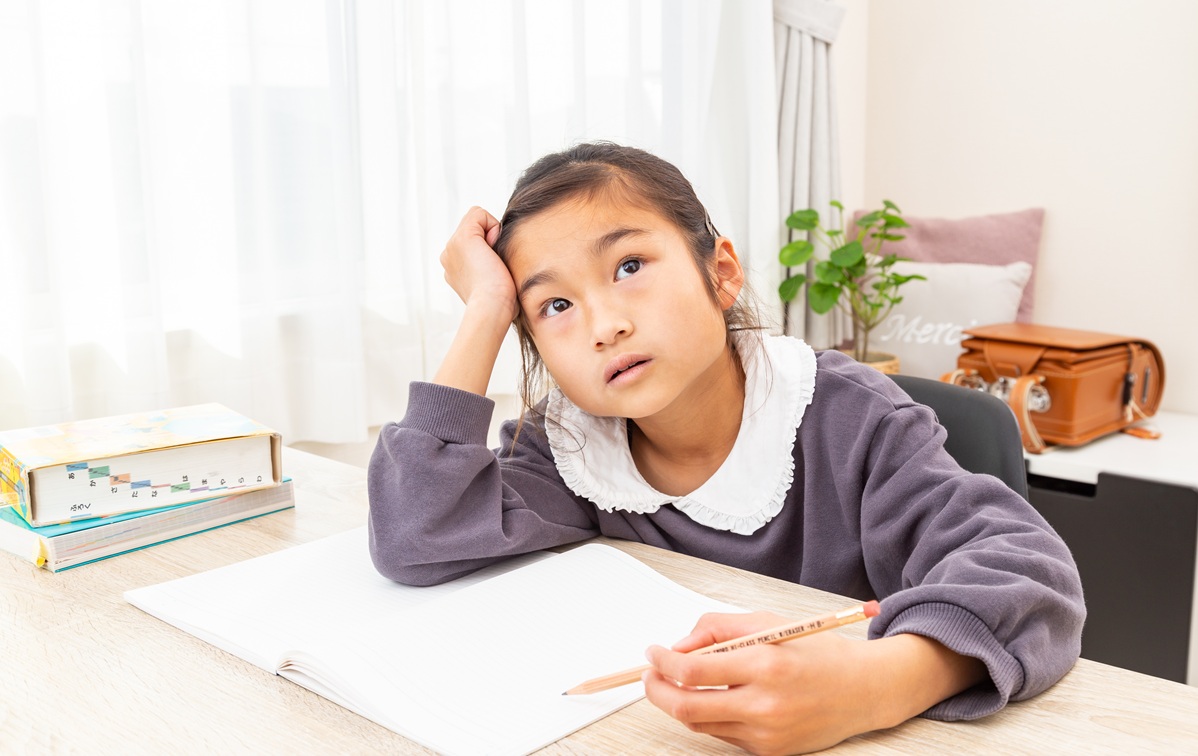
中学受験では致命傷になりかねない「ケアレスミス」。ミスがなくならない子の親に多い特徴とは?ミスを起こす要因やその予防対策など、ケアレスミスについて徹底解説いたします!
CONTENTS:
5.まとめ~もうすぐ本番!ふだんとは違う緊張感
1. ケアレスミスがなくならない子の親に多い特徴とは?
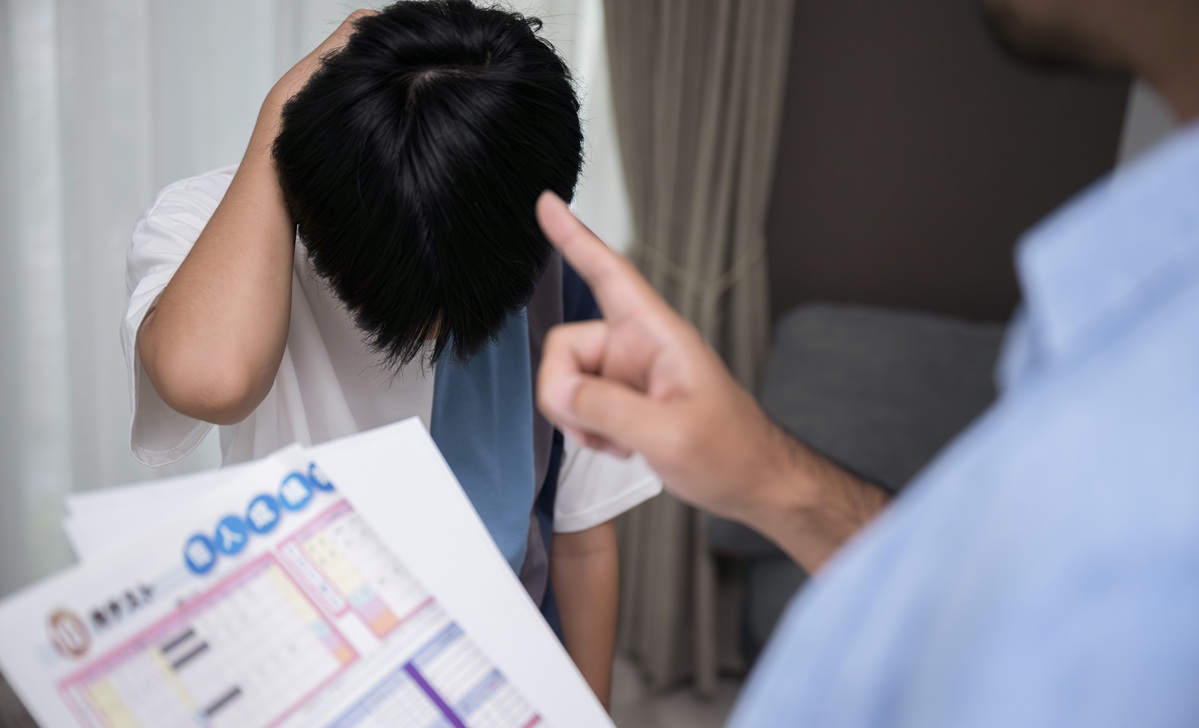
親の行動チェックリスト
最初にケアレスミスをしやすい子の親に当てはまるか否かチェックしてみましょう。ふだんの行動で以下に当てはまると思うものにいくつでもチェックを入れてください。
□ 三者面談等でよく「うちの子はケアレスミスが多い」と相談している
□ 成績の結果だけ見て、戻ってきた解答用紙を見ていない
□ 多少睡眠時間を削ってでも勉強させている
□ つい「つまらないミスばかりして」とグチグチ言ったり怒ったりしてしまう
□ 間違いノートを作っていない
上記のうち1つでもチェックが入れば、子どもがケアレスミスを起こしやすい可能性があります。複数入った場合はとくに要注意です。次に詳しく解説いたします。
① 「ケアレスミスが多い」と相談
三者面談やママ友など、子どもがいる前で「うちの子は本当にケアレスミスが多くて」「何度言ってもぜんぜんなくならないの」などと言うのは避けましょう。
親としては子に直して欲しくてわざと子の前で言っているのかもしれませんが、それは本人にとって「擦り込み」になり、逆効果です。「ああ、自分ってミスばかりする人間だ」「ダメなんだ」と思い、余計にミスを誘発する可能性があります。
愚痴りたいときもあると思いますが、ネガティブな発言は少なくとも子どものいない時にしましょう。
② 返却された解答用紙を見ていない
模試など試験があった場合、その結果(成績)は気にして確認しますが、返却されたテストの解答用紙等まではチェックしない親がほとんどではないかと思います。
結果だけを見ても、なぜ間違えたのか、どの問題をどのように間違えたのかまではわかりません。模試などは練習ですから、「結果そのものよりも、なぜどうして間違えたのか」ということのほうが大事です。
それがわからなければ、ケアレスミス対策もしようがなく、なかなか改善しないでしょう。ぜひ解答用紙を見て、計算の仕方や文字の間違いなど、何をどう間違えたかを確認してあげてくださいね。
③ 睡眠時間を削って勉強させる

いくら受験生でも睡眠時間を削ってまで勉強させるのは、感心できません。中学受験生といってもまだ小学生。睡眠不足では頭も働きません。
集中力、注意力も散漫になるため、自ずとミスも増えてしまいます。個人差はありますが、子どもにはぜひ十分な睡眠時間を与えてあげましょう。
④ つい愚痴ったり怒ったりしてしまう
これも①と同じ理由で、「あなたは本当によくケアレスミスばかりする子ね」「どうしてこんなにミスばかりするの」などと、いつもくどくど文句を言ったり怒ったりしていると「擦り込み」が起こります。
「自分はどうせダメだから」「どうせミスするに決まってる」「またグチグチ言われるのはたまらない。もう受験やめたい」などとどんどん負の感情が大きくなり、悪循環に陥ります。
大事なことは子どもに文句をいうのではなく、「いま間違いがわかってよかったね」「どうしてこの問題を間違えたかわかる?」と、いっしょに間違えた原因を考えることです。その際、親が「ほら、ここの計算が間違ってる」「こんな汚い字で書くからでしょ」と指摘するのではなく、子ども自身に考えさせ、間違った原因を認識させることが大切です。
⑤ 間違いノートを作っていない
ケアレスミスをなくすには、「間違いノートの作成」が効果的です。東大出身の謎解きクリエイター松丸亮吾さんのお母さまが作成した「バツ(✕)ノート」は有名な話で、間違った問題をノートに貼ってオリジナルの問題集のようなものを作り、間違えなくなるまでやり続けたそうです。
これは、テストや模試などの間違い直しを徹底させるための専用ノートで、なぜ間違えたのか、どうすれば間違えなくなるのか、自分で考えながら間違った問題を解き直すので、いつの間にか間違えなくなります。
ここで注意したいのは、難しい応用問題しか間違い直しをしないことです。「ケアレスミスだから間違い直しは不要」は大間違い。ケアレスミスだからこそ間違い直しをして、どうして間違ったのかを見直してください。そのためにも、できれば間違いノートを作成してあげてくださいね。
2. 「ケアレスミス=小さなミス」ではない!

「うちの子はケアレスミスが多い」と軽んじていませんか?
「うちの子はミスが多くて困ります」などと笑いながら話す親をよく見かけます。その裏には、「本当はうちの子はできるのに、あんなつまらないところで落としてもったいない」と言いたいところなのでしょう。しかし、失点は失点です。
「ちょっとした問題の読み間違いだから、60点だったけど本当は80点は取れていた」などという発言もよく耳にします。しかし試験出題者からすれば、どこをどうとっても「あなたは60点です」としか言いません。
結果としては、どのようなミスをしたかではなく、実際に取れた「点数」だけです。その点数が合格点に達していれば「合格」、達していなければ「不合格」、極めてドライなものです。
ケアレスミスは性格のせい?
よく「うちの子はおっちょこちょいで…」や「うちの子はあわてんぼうで問題を最後まで読まない」などと子どもの性格のせいにしている親を見かけます。性格なので仕方ないと諦めてしまうと、矯正できるものもできなくなります。
ケアレスミスは誰しもしてしまうミスですが、誰でも直すことのできるミスでもあります。
それを性格のせいにして、直すための策を考えないというのは取れる点数を簡単に手放してしまっているのと同じで、たいへんもったいないことです。
ケアレスミスは深刻なミス!合否は1点で決まる!
ケアレスミスを「ただの計算間違い」「ただの書き間違い」というように、あまり重要視しないで見過ごしてしまうことは、受験生にとって最も危険な行為です。
無駄な失点は本番での致命傷になりかねません。それを踏まえ、今のうちに無駄な1点を失わないよう、ケアレスミスは重大なミスと緊張感を持って対策していく必要があります。
「うちの子はミスが多くて…」などと愚痴っている場合ではないのです。いつまでもケアレスミスがなくならないのは大問題と考えましょう。今日から「ケアレスミス=小さなミスではなく」「ケアレスミス=深刻なミス」と認識するようにしましょう。
3.ケアレスミスを起こす要因

ケアレスミスは不注意によるミスですが、ケアレスミスをする子どもは毎回複数のミスをしています。それはなぜなのでしょうか。
ケアレスミス対策が不十分!
何度も同じようなケアレスミスをしてしまうのは、まずいちばんにケアレスミスを重要視せず「ケアレスミス対策」をしっかりしていないことがあげられます。その多くが返却されたテスト等の間違い直しをきちんと行っていないことにあります。
算数に多いケアレスミス
算数の間違い直しは後半の難しい問題だけ行って、前半の計算問題は「いつもだったら解けるからだいじょうぶ」「こんなかんたんな問題はできる」「ちょっとしたミスだから」と行わない人がいます。
このような生徒は、次も前半の計算問題で失点する可能性が高いでしょう。かんたんと思えるような計算問題をいちいち間違い直しするのは時間の無駄のようで面倒に感じるかもしれませんが、かんたんに思える問題も他の難しい問題と同様に丁寧に直し、間違えた原因を把握することが大切です。
これを繰り返していると、「また同じ間違いをしてしまった」「もう間違い直しをするのはいやだ」、「次は絶対同じ間違いはしないぞ」という意識が芽生えるようになり、ケアレスミスをしないようになっていきます。ケアレスミスを軽視して、間違い直しをしなければこのような意識も芽生えません。
国語・理科・社会に多いケアレスミス
国語や理科、社会で特に多いケアレスミスが、答え方の間違いです。例えば、選択問題で「正しいものを選びなさい」「間違っているものを選びなさい」「正しいものをすべて選びなさい」などという指示があるのに、違うものを選んでしまっているようなミスです。
また、語句を答える問題で、「漢字で答えなさい」「ひらがなで答えなさい」「カタカナで答えなさい」などと指示があるのに、よく読まずに漢字をひらがなやカタカナで書いて失点してしまうミスです。
このようなミスはよく起こるので、誰しも一度は思い当たることがあるのではないでしょうか。「わかっていたのにもったいない」と悔しく思ったことでしょう。それなのに、同様のミスを何度もするのは、きちんと間違い直しをしていないからだと思われます。
入試は満点を取るような試験ではありません。いかにケアレスミスなく正確に解き切れるか、いかに失点を防げるかが合否を分けるポイントです。
4.今日から始めるケアレスミスをなくすための4つの対策

ケアレスミスの要因やよく起こるミスをお伝えしましたが、それではどのように対策したらいいのでしょうか。ふだんから気をつけたい4つのケアレスミス予防対策についてご紹介します。
① 問題のキーポイントに線や〇をつける
最初にやってもらいたいのは、「問題文の答え方の部分に線や〇をするクセをつける」ことです。算数や理科では「cm」や「ml」など単位を指定されたり、図形問題では円周率を3.14ではなく、まれに「3」や「22/7」などで求めなさいなどと指示される出題もあります。
国語では漢字の画数を「漢数字で書きなさい」などと指示されているのに、算用数字で書いてしまったりするミスがあります。答えそのものがあっていても、指示と違う答え方をすれば失点となります。
これには、「最後まできちんと問題文を読んでいるか」「注意力、集中力があるか」ということも問われている試験だという出題者の意図が感じられます。
答え方は問題文の最後に書かれていることが多いので、問題文を最後までしっかり読み、単位の「cm」や「22/7」、「漢字で」などという答え方の部分には線を引いたり〇をつけたりするなどして、間違えないように注意してください。
試験中最後に見直しをする際にも間違いに気づきやすくなるので、日ごろから問題文の答え方の部分には線や〇をつけるクセをつけるようにしましょう。
② 計算用紙の使い方
特に算数や理科の試験時の注意点として、途中計算をしている場所によるミスの誘発も多くあります。問題用紙などの空白部分を計算する場所として利用すると思いますが、同じ問題なのに、あちらこちら裏なども使っていろいろな場所で計算している受験生がいます。
時間がないなか、つい目についた空白を使いたくなる気持ちもわからないでもありませんが、途中でミスに気がついてもどこに何を書いたかがわからなくなって時間のロスになりますし、そもそも転記ミスや間違いの原因にもなります。
少なくとも同じ問題の計算は、一か所で行うようにしましょう。ある1つの問題を用紙の右下の空白部分に書いたのなら、その問題については全てその近辺で計算を行うほうがミスは減ります。
③ 文字は丁寧に書く

ケアレスミス予防対策として、基本中の基本で最も大事なことは「文字や数字を丁寧に書く」ということです。自分は正しい答えを書いたのに、数字が読みづらくて失点したという経験はないでしょうか。
「“5”と書いたつもりが“6”と判断された」や、「“7”が“1”や“9”に見えた」などというのはよく聞く話です。また、記号で答えるのに「ア」にも「イ」にも見えるような字を書いて失点するケースも少なくありません。
塾などでは厳重注意で大目に見てもらえても、本番の入試では正解が「ア」や「イ」のどちらであってもまぎらわしい字は間違いとして扱われます。漢字指定の場合はなおさらです。漢字は「楷書体で画数に注意して書く」ことが基本で、続け字にしないで一画一画丁寧に書くことが必須です。
それには日ごろから丁寧な字で書くクセをつけておくことです。ふだん適当にサササッと書いているのに、本番だけ丁寧には書けないものです。とくに試験では時間制限もあるのでよけいに焦って崩し字になりがちです。
本人や親が読めても、採点者が読めなければ失点になる恐れがあります。ふだんから丁寧な字で書くクセと、とくに模試などの時間制限のあるテストでは丁寧なしっかりした字を書くように意識しましょう。
④ 制限時間内に解く
ケアレスミス予防対策の最後は、ふだんの演習から制限時間を決めて問題を解くクセをつけることです。ケアレスミスをする要因の一つが「時間に追われて慌ててしまう」ことにあります。
家で間違い直しをすると普通に解けるという人は、これに当てはまります。時間に追われる心配がない、リラックスした状態で問題に取り組めればミスをせず、慌てるとミスをするタイプなのかもしれません。
そのため、ふだんから「時間に追われる状況に慣れておく」のも有効な対策となります。緊張感をあえて自分に課して訓練するのです。ただし、家と試験会場とは全く違います。本番の試験会場は、張りつめた空気感の中でライバルたちの鉛筆を動かす音だけが聞こえるという独特の環境です。
家でそのような空気感を作ることは難しいですが、少しでも緊張感を高めるという意味で、せめて制限時間を決めて本番さながらの演習を行うのは非常に意味のあることです。ぜひ家族で協力して家庭内でもそのような場を作ってあげるようにしてくださいね。
5.まとめ~もうすぐ本番!ふだんとは違う緊張感
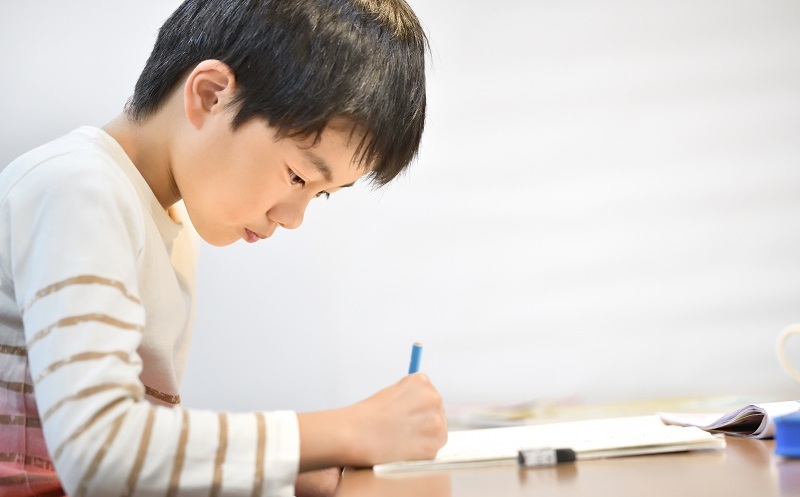
今回は中学受験のケアレスミスについて詳しくお伝えしました。小学6年の受験生にとっては、入試本番はもうすぐそこです。日ごろ塾で受けている模試とは比較にならないほど緊張し、ふだんはしないようなケアレスミスをする可能性も高くなります。
貴重な1点を争う中学入試本番でつまらないケアレスミスをしないように、ぜひ親御さまも協力してあげてください。そして最後に、「ケアレスミスは小さなミスではなく深刻なミス」ということだけでも覚えておいてくださいね。
※「ケアレスミスがなくならない」や、親の「時間がとれず、ケアレスミス対策が十分にできない」、またはその他受験のことで何か悩みや不安がある場合は、思い切って残りの数週間だけでもプロの家庭教師に相談してみましょう。本格的なケアレスミス対策ができるのも今のうちですよ!

ケアレスミスに関する不安も解消!
中学受験のプロが個人に合った学習指導を行います。