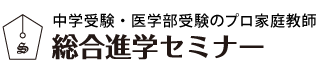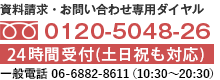じめじめと蒸し暑い日が続き、心身のバランスも天候によって左右されやすいこの時期、食事による毎日のコンディション作りがより一層重要になってきます。
前回は集中力を作る食事法として食事の摂り方についてご紹介しましたが、今回はより具体的な栄養素や気を付けたい食品についてのポイントをご紹介します。

◎脳を働かせ集中力に繋がる栄養素
前回の記事では、目に見えない気分や感情、知的機能(集中力・記憶力など)をコントロールする神経伝達物質の主材料となるタンパク質の重要性について触れました。
脳を働かせ機能を活性化させるためには、さまざま神経伝達物質が適切に生成・分泌されなければならないのですが、それにはタンパク質に加えて次のような栄養素が特に重要になってきます。
◆ビタミンB群
ビタミンBにはB1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチンの8種類があり総じてビタミンB群と呼びます。ビタミンB群は主に食べた物をエネルギーや筋肉、新しい細胞などに作り変える際に必要となってくる栄養素です。
神経伝達物質においても、タンパク質を主材料として新しい各種物質を生成する過程において必要となります。
また、ビタミンB群は8種類ありますが互いに作用し合いながら体内で働くため、8種類全てをさまざまな食材から摂取することで効率よく働くことが出来ます。
◆鉄
鉄は血の成分となる赤血球の主材料としてよく知られていますが、その他にもエネルギーの生成や、コラーゲンの形成、免疫機能などさまざまな重要な役割を担っています。
神経伝達物質の生合成の過程においても、やる気ホルモンや幸せホルモン、落着きホルモン、睡眠ホルモンなどは鉄が必須の材料であるため、鉄欠乏は集中力の低下、学習能力の低下、うつ症状や睡眠トラブルの原因にもなります。
◆マグネシウム
マグネシウムは骨の構成成分として骨や歯の強化に欠かせない他、体温や血圧の維持、糖質・脂質・タンパク質の代謝を助けるなどの働きがあります。
神経伝達物質の生成過程においては、睡眠ホルモンであるメラトニンや心の安定に関わるGABAの生成時に必須であるため、不足すると不安、不眠、集中力の低下などが引き起こされやすくなります。
◎やる気を作る腸内細菌
神経伝達物質には大きく分けて、幸福感や睡眠を司るセロトニン、やる気や闘争心を司るノルアドレナリン、落着きを司るGABAの3つがありこれらのバランスによって、感情などがコントロールされています。
これらの物質の多くは腸の中の腸内細菌が作り出しており、とくにセロトニンに関してはその90%が腸で合成されています。
そのため、良好な腸内環境で元気な腸内細菌を保ち続けることが、勉強におけるやる気や集中力にも大きく影響してきます。
<レシピ>
~一皿で栄養バランス整う!具沢山混ぜそば~
【材料】(1人分)
- ・そば(生麵)……80g
- ・豚バラ(薄切り)……60g
- ・ニラ……2~3本
- ・にんにく……1/2片
- ・ごま油……小さじ2
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・酒……大さじ1
- ・しょうゆ……大さじ1/2
- ・みりん……大さじ2/3
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・細ネギ……適量
- ・かつおぶし……1g
- ・卵黄……1個
- ・かけつゆ……大さじ1
- (めんつゆはかけつゆ濃度に希釈してください。)
- ・あれば、すだち(レモン)……適量

【作り方】
- ① 豚バラは食べやすい長さに切り、ニラは1㎝幅に切る。細ネギは小口切りにし、にんにくはみじん切りにする。
- ② フライパンにごま油を入れてにんにくを加えたら香りがたつまで熱し、豚肉とニラも入れ火が通るまで炒める。
- ③ そこにAを加えてさらに炒めたら、火を止めて粗熱がとれるまで置く。
- ④ 沸騰したお湯でそばを茹でて、ざるにあげて冷水で洗う。
- ➄ 器にそばを盛りその上に③の具材をのせ、卵黄、細ネギ、かつおぶしも盛りつける。
- ➅ 最後にかけつゆとお好みですだち(レモン)を絞りかけたら出来上がり。
*すべての具材を混ぜながら食べてください。

豚肉や卵にはタンパク質の他ビタミンB群も豊富に含まれており、そこにビタミンCやβカロテンが豊富なニラやネギ、食物繊維に富んだそばを合わせました。
脳の疲労回復だけでなく腸内環境も整えてくれ、さまざまな栄養素が美味しく摂れる一皿です。
◎注意したいカフェイン摂取
カフェインと聞くとコーヒーや紅茶が思い浮かび、小学生ではまだあまり飲まないだろうと安心しているかもしれません。
しかし、カフェインはコーヒーや紅茶だけでなく、チョコレートやココア、ガム、清涼飲料水、緑茶、薬といったものの中にも含まれており、知らず知らずのうちに子供も摂取しています。
そもそもカフェインとは、豆や茶葉などに含まれる植物由来の食品成分の一種です。
カフェイン自体には興奮作用があり摂取することで、疲れが和らぐ、集中力が上がる、眠気が覚めるといった感覚を得ることができ、薬やエナジードリンクの材料として用いられることもあります。
その反面、代謝に時間がかかり体内に長時間留まることや、過剰摂取により脳への刺激が強くなり過ぎることで、落ち着かない、眠れない、吐き気や嘔吐、頭痛などの症状が現れ、子供においては成長の妨げの一因になることもあります。
◉エナジードリンクの落とし穴
運動後や勉強で疲れた時など、元気を出すための着付け薬のような感覚でエナジードリンクを飲んだ経験はないでしょうか。
エナジードリンクはカフェインを含んでいるため、飲んだ後は頭がスッキリして疲れが取れたように感じるかもしれません。
しかし、製品にもよりますがコーヒーと同量あるいはそれ以上のカフェインが含まれているだけでなく、飲みやすくするために多くの糖質も含まれているため、カフェイン・糖質両方の過剰摂取に繋がりその後の不調の大きな原因となりかねません。
◉カフェインとの付き合い方
カフェインのメリット・デメリットを上記しましたが、子供においては、大人とは違ったカフェインとの付き合い方が必要になってきます。
とくに子供であればその摂取許容量も大人と比較して少なく、摂取したカフェインの代謝も遅いため過剰摂取に陥らないように注意が必要です。
また個人差も大きく、カフェインに敏感な場合や不調を起こしやすい場合には、摂取を控えることを検討するなどより慎重になることも必要です。
<レシピ>
~ホッと一息!すっきりジンジャーレモネード~
【材料】(作りやすい分量)
- ・しょうが……150g
- ・キビ糖……150g
- (てんさい糖、黒糖など未精製のものがおすすめ)
- ・水……150ml~200ml
- ・レモン果汁……30ml

【作り方】
- ① 耐熱用の瓶を煮沸消毒し粗熱をとっておく。
- ② しょうがはよく洗って皮ごと薄くスライスする。
- ③ 小鍋にしょうがとキビ糖を入れて混ぜ合わせ、水分が出てくるまで30分以上置く。
- ④ 水を加えて弱~中火にかけてアクを取りながら15~20分程煮る。
- ➄ 粗熱が取れたらレモン汁を加えて、煮沸消毒した瓶に入れる。
- ⑥ 水やお湯、炭酸水など好みの飲料で割る。(目安は4~5倍希釈)
*シロップは冷蔵保存で4日ほどを目安に保存できます。
*お好みでミントやローズマリーなどのハーブを加えてもさらにスッキリ美味しく召し上がれます。

しょうがに含まれるシネオールといった成分や、レモンに豊富なビタミンCには疲労回復効果があり、運動や勉強で疲れた際に摂取すると効果的です。
また、上白糖ではなくキビ糖や黒糖、てんさい糖などの未精製の糖を使うことで、ミネラルなどの栄養成分も摂取することが出来ます。
ホッと一息つきたい受験生のブレイクタイムに、おすすめしたいノンカフェインの飲み物ですのでぜひ一度作ってみて下さい。