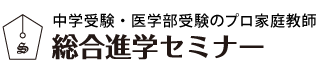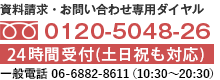食欲の秋が近づいてくるこの頃食事は楽しみであると同時に、受験生にとっては何を食べるかが重要となってきます。
それに加えて、それらをより効果的に摂取するためには、量やタイミングも重要になってきます。
以前、体内時計と食事の関係についてもご紹介しましたが、とくに受験生にとって朝・昼・晩の1日の食事は、それぞれのタイミングに意味やねらいがあり、それらに応じた食事内容と量を意識することが、勉強のパフォーマンスや心持ち、体調などを向上させる鍵になってきます。
そこで今回は、1日の中でのそれぞれの食事のバランスを整えるポイントについてご紹介します。

◎朝食を制するものは1日を制す
勉強や仕事などの作業効率に大きな影響を与え、1日の行動や考え、心持ちを整える上で最も重要になってくるのが朝食です。
以前の記事でも朝食の重要性に触れましたが、朝は身体が枯渇状態であり食べた物の吸収や代謝が盛んに行われるため、必要な栄養素をしっかり摂取することが重要です。
①肉・魚・卵(タンパク質)
朝食では、寝ている間に分解、消費されたアミノ酸を補うためのタンパク質の摂取が重要になってきます。
タンパク質(アミノ酸)は体のあらゆる細胞の材料として毎食必ず摂取する必要がありますが、とくに朝食においてはその必要性と吸収率は最も高くなります。
思考力・記憶力・集中力などの源となる神経伝達物質もアミノ酸を材料として作られているため、朝から不足しているアミノ酸をしっかり補うことが大切です。
②野菜・果物・豆類(ビタミン・ミネラル・食物繊維)
ビタミンやミネラル、食物繊維、水分を多く含む、野菜や果物も朝に摂ることで腸の蠕動運動を促し朝の排便リズムの確立や、良好な腸内環境に繋がります。
③ごはん(糖質)
糖質は朝・昼・晩の3食のうちでは朝に摂るほうが、1日の行動エネルギーとして消費されやすいためおすすめです。
ただ、摂りすぎや、糖質のみの食事(菓子パン、甘いシリアルなど)は、血糖値の乱高下を引き起こし朝から1日の不調を招く原因となるため、注意が必要です。
具材の入ったおむすびや、雑穀米、混ぜご飯などを適量摂取するのが良いです。
これらを踏まえて、朝食ではタンパク質を中心に、それと同じ量程度の野菜を付け、その上で適量のごはんやおにぎりなどを付けると食事バランスが整ってきます。
また、1日の全体の中でも、朝食で量や食材の種類などをより多く摂取できることが理想的です。
<レシピ>
~朝食にも!優しいカルビクッパ~
【材料】(3人分)
- ・牛肉(薄切り)…150g
- ・ニラ……3本
- ・長ネギ……1本
- ・人参……1/3本
- ・ごま油……大さじ1
- ・にんにく、しょうが(すりおろし)……各小さじ1/2
- ・水……400ml
- ・ごはん……150g
- ・卵……2個
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・鶏がらスープの素……大さじ1
- ・しょうゆ、みりん、酒……各大さじ1
- ▲▲▲ A ▲▲▲

【作り方】
- ① ニラは1~2㎝に切り、長ネギは斜め切りにし、人参は千切りにする。
牛肉は食べやすい大きさに切り片栗粉(分量外)をまぶしておく。 - ② 鍋にごま油をひきにんにく、しょうがを入れ中火にかけて香りがたってきたら、長ネギ、人参、牛肉を加えて炒める。
- ③ 具材に火が通ってきたら水を入れてひと煮たちさせ、アクを取り除いたらAを入れる。
- ④ そこにご飯を入れて混ぜたらニラを加え、最後に溶き卵を回し入れふんわりと固まったら出来上がり。

クッパにすることで一皿でお肉や卵(タンパク質)、野菜(ビタミン、食物繊維)などさまざまな食材をスープごと栄養を余すところなくしっかり摂れ、少量のごはん(糖質)でも満足感が高くなります。
時間や食欲のない朝にもピッタリですので是非一度作ってみて下さい。
◎疲労を感じない午後のための昼食
昼食は午後以降の活動の良し悪しに大きく影響してきます。
例えば、昼食後に眠気に襲われたり、午後はボーっとして集中しづらい、夕方近くになると疲れを感じる、学校から帰宅後休憩しないと動けないなどといった経験はないでしょうか。
これらは、昼食の量や内容により引き起こされている不調かもしれません。
では、午後から万全のコンディションで活動するためにはどのような食事を摂ればよいのでしょうか。
①タンパク質
昼食においても、食べ溜めできないタンパク質の摂取を第一に考えることが重要です。
筋肉や皮膚、内臓だけでなくホルモンや酵素などあらゆる細胞の主材料となり、摂取したタンパク質によって今この時も体の細胞は作り変えられています。
午後からの活動エネルギーのために、多少高脂質のタンパク質を含む食事も昼食に摂るのがおすすめです。
②ビタミン・ミネラル・食物繊維
昼食時に野菜などからしっかりと食物繊維を摂取することで、夕食後の血糖値の上昇を抑えることが出来ます。
主菜や副菜などのおかず中心の食事を腹八分目のバランスが最適になります。多少油の多いハイカロリーのおかずも昼食時であれば摂るのに問題ないと思いますが、食べ過ぎや、昼食における糖質の過剰摂取・糖質に偏った食事(おにぎり、パン、ラーメンのみなど)の摂取は夕方近くの疲れや不調の原因になるため、ここでも注意が必要です。
学校で給食を食べる際も食べる順番を、最初におかずを食べた上で、最後にごはんやパンなどの糖質を食べることで血糖値の乱高下を防ぎやすくなります。
◎睡眠を整える夕食・夜食
夕食は、睡眠中の成長や回復、睡眠の質に大きな影響を与え、ひいては学習の定着や翌日のメンタルを整える上でも重要になってきます。
受験生においては、夕食を塾の前後に分けて食べる方も多いと思います。
また、夕食後も勉強し夜食を摂る日もあるかもしれません。
そのような場面で、どのような物を摂るのが良いのでしょうか。
◆塾の前の夕食
就寝中に必要となるタンパク質を中心に、ごはんなどの糖質は勉強をするための脳のエネルギーとして必要ですが、食後の眠気や不調が出ない程度の量に抑えることが重要です。
また、食事直後や、満腹状態では、消化に多くのエネルギーが使われたり、セロトニンの分泌増加により副交感神経が優位になったりするため集中力が低下します。
できるだけ時間に余裕をもって食事は腹八分目程度にするのが塾前の夕食のポイントになります。
◆塾の後の夕食・夜食
昼食時に野菜などからしっかりと食物繊維を摂取することで、夕食後の血糖値の上昇を抑えることが出来ます。
夜の遅い時間に食べがちな夕食や夜食は、消化吸収に時間のかかる脂質や食物繊維は避ける必要があります。
加えて、夜は体内の脂肪燃焼の働きも弱まるため脂質と糖質でできた食品の摂取は控える方がよいです。
また、空腹で寝ると睡眠の質が低下するため、就寝前の空腹時には血糖値を上げない消化の良いタンパク質を少量摂取することもおすすめです。
<レシピ>
~簡単!豚と大葉のチーズ薄焼き~
【材料】(1人分)
- ・ライスペーパー…1枚
- ・卵……1個
- ・シュレッドチーズ……30g
- ・豚バラ肉……2枚
- ・大葉……4枚
- ・ポン酢……適量
【作り方】
- ① フライパンに薄く油をひきライスペーパーをおき、その上に卵を割り黄身をほぐしながら広げる。
- ② その上にチーズを散らし、豚バラ肉(適度な長さに切る)、大葉の順にのせて中火にかける。
- ③ 卵が固まってきたら半分に折りたたみ、フライ返しなどで上から軽く押さえつけ、片面1分半ずつ焼き両面に焼き目が付いたら火を止める。
- ④ 食べやすい大きさに切り、お好みでポン酢をかけたら出来上がり。

豚肉、チーズ、卵などさまざまなタンパク質を1枚で摂れる食べやすい薄焼きにしました。
ライスペーパーを使うことでフライパン一つで簡単にできるので、夜食や朝食にもおすすめです。