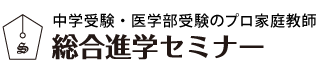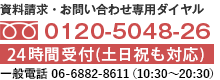長時間(長期間)勉強に向き合うことで、時には心も頭も余裕がなくなってしまうことがあります。
いくらたくさん勉強しても、気持ちを整理する余裕や新しい情報を入れる隙間がなくては、なかなか効率的に勉強することは難しくなってきます。
それは、受験生を支え伴走している家族も同様です。
やるべきことに追われる忙しい日々の中で、そのような余裕を作り出せるのが食事ではないでしょうか。
食事には体に必要な栄養素を摂取するという大きな目的の他に、美味しい物を食べる楽しみや幸福感を生み出す力があります。
そのような食事はストレスの軽減、集中力の向上、心の安定などにも大きく影響してきます。
では、お腹がすいたから、時間がきたからただ何となく食べる食事と、心も頭もリラックスさせて、幸せな時間を作り出すことが出来る食事では何が違うのでしょうか。

◉食事環境
塾などで食事時間を左右される受験においては、夜遅く帰ってきて一人で食べることもしばしばかもしれません。
食事を共にしなくても近くにいて、その日あった勉強以外の話を聞くことも良いかもしれませんし、反対に、思春期に差し掛かる時期においては会話がかえってストレスになることもあるかもしれません。
しかし、どのような場合であってもその時間だけは少し静かに食事に集中できる環境を整えることが重要です。
◇毎日テレビやスマホを見ながら食べるのではなく、目の前の食事そのものに意識がむくようにする日も作る。
◇五感を働かせ食べ物の味、色、匂い、食感、温度などを少し意識して感じながら食べられるように工夫する。
◇食事の前や途中で、今自分が空腹なのか満腹なのかなど体からのシグナルにも注意を払って適量食べられるようにする。
(「どれくらいお腹がすいている?」、「ゆっくり食べてみて」、「何が入っていると思う?」といった声かけもよいです。)
<レシピ>
~秋のドライカレー~
【材料】(4人分)
- ・合いびき肉…300~350g
- ・いちじく……2個
- ・れんこん……100g
- ・なすび(中)……1本
- ・しめじ……80g
- ・玉ねぎ……1/2個
- ・にんにく……1片
- ・しょうが……1片
- ・バター……15g
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・カレー粉……小さじ1
- ・ケチャップ……大さじ3
- ・中濃ソース……大さじ2
- ・しょうゆ……小さじ1
- ・塩……小さじ1/4
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・ごはん……適量

【作り方】
- ① にんにくとしょうがはみじん切りにする。
いちじく、れんこん、なすび、しめじ、玉ねぎは粗みじん切りにする。 - ② フライパンにバターを熱して溶かしたら、にんにく、しょうがを入れて香りがたつまで炒め、いちじくを加えてトロっとするまでさらに炒める。
- ③ そこにれんこん、なすび、しめじ、玉ねぎを入れて全体がしんなりするまで炒め、ひき肉を加えたら火が通るまでじっくり炒める。
- ④ Aを加えて全体をしっかり混ぜながらひと煮たちさせたら、塩(分量外)で味を調える。
- ⑤ お皿にご飯を盛りその上から④をかけたら出来上がり。
*お好みで半熟卵などをのせて一緒に食べても美味しいです。

旬の秋の食材を使い、食欲そそるドライカレーにしました。
シャキシャキとしたれんこんの食感や、コクのある優しい甘みのいちじくなど秋の食材を五感で楽しめる一品です。
季節を感じる会話のきっかけともなりますので、是非一度作ってみて下さい。
◉食事内容
好きな物を好きなだけを食べることは、一見すると楽しく、幸せなことのようにも思えます。
もちろん、そのような日を作るのも良いですが、好きな物に偏った食生活が続くと今度は体や心に不調が現れてきます。
というのも、心も体も食べた物からできているため、それらを作る上で必要となる栄養素が不足すると体はSOSのサインを出し始めるからです。
そのため食事内容やバランスも重要になってきます。
好きな物を意識しつつ、旬の食材を取り入れる、タンパク質を中心にする、とくに遅めの夕食では糖質は控えめにするなどの工夫が必要になってきます。
また、疲れたときや季節の変わり目などには以下のような栄養素の摂取がポイントになります。
<ストレス時>……ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB群
ストレスがかかると、体内では抗ストレスホルモンというものを分泌してストレスに対抗します。
この抗ストレスホルモンの合成に大量に必要となってくるのがビタミンCです。
また、このホルモン生成を補助する役割を担っているのがビタミンB群であり、ストレス時にはこれらのビタミンの消費量が著しく増えるため、意識的に補っていく必要があります。
加えて、ストレスがかかった際に体内で発生する活性酸素を抑える働きのあるビタミンEも同時に摂取を意識することが、ストレス対策として有効です。
<脳疲労>……ω3系脂肪酸
DHAやEPAといった魚の脂に含まれるω3系脂肪酸は、脳細胞間での神経伝達物質のやり取りをスムーズにしたり、体内での炎症を抑えたりすることなどにより、脳や体の疲労症状を軽減してくれる働きがあります。
<心が不安定>……タンパク質、ビタミンB群、鉄、マグネシウム、亜鉛
心の感情を作る神経伝達物質はタンパク質(アミノ酸)を主材料とし、ビタミンB群、鉄、マグネシウム、亜鉛といった栄養素の補助を受けて生成されます。
(これらの栄養素は、神経伝達物質だけでなく、その他の細胞や代謝を回すための材料としても用いられています。)
そのため、食事からタンパク質やビタミンB群、ミネラルなどが不足すると、落ち着かない、集中しづらい、ぼーっとするなどの不調が起こりやすくなります。
◉食事のタイミング
毎日の食事を時間が来たから無意識に食べているといった人もいます。
(とくに、忙しく食欲も湧きずらい朝食などには多いかもしれません。)
しかし、私たちの体には体内時計というものが備わっており、これによってそれぞれの時間の栄養素の吸収や代謝効率も変わってくるため、3食の食事にはそれぞれに異なった意味(目的)があります。
昼:午後からの活動を円滑にするための食事 (脂肪を蓄積しづらい時間帯になるため、しっかり食べたいものは昼食で!)
晩:睡眠の質を高め、成長ホルモンの分泌を促すための食事
(脂肪が蓄積されやすい時間帯になるため脂質は軽めにし、夜間の血糖値を安定させるために糖質も適量にとどめておく
また、運動後のように消費や枯渇が激しい状態(の直後)で摂取した栄養素の吸収率は非常に高くなるため、体の状態に応じたタイミングを見計らい食事を摂取することも重要となってきます。
・起床時……水分、タンパク質(アミノ酸)、エネルギー
・運動……タンパク質(アミノ酸)、エネルギー、ミネラル
・勉強……エネルギー、タンパク質(アミノ酸)、ビタミンB群、鉄
・発熱や感染……ビタミンC、ビタミンB群
・ストレス……ビタミンC、タンパク質(アミノ酸)、ビタミンB群、鉄
<レシピ>
~秋鮭と根菜の甘辛炒め~
【材料】(4人分)
- ・秋鮭(皮なし)…3切
- ・れんこん……150g
- ・さつまいも(小)……1本
- ・オクラ……4本
- ・ごま油……大さじ2
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・コチュジャン……大さじ1
- ・みりん……大さじ2
- ・しょうゆ……大さじ1
- ・はちみつ……小さじ2
- ・酢……大さじ1
- ・水……大さじ2
- ・おろしにんにく……1片
- ▲▲▲ A ▲▲▲

【作り方】
- ① れんこんは皮をむき5㎜幅程のいちょう切りにし酢水につけたら、水気をきる。
さつまいもは食べやすい大きさに切る。オクラは塩ゆでし、1/2に切る。 - ② 秋鮭は食べやすい大きさに切り、塩(分量外)をまぶし5分程置き出てきた水分をふき取り、片栗粉(分量外)を全体に軽くまぶす。
- ③ Aの調味料を合わせて混ぜる。
- ④ フライパンにごま油をひいたら、秋鮭を両面火が通るまで焼く。
- ⑤ 秋鮭を取り出したらごま油を少し足して(分量外)、れんこん、さつまいもを入れ両面に焼き色がつくまでじっくり焼く。
- ⑥ そこに秋鮭、オクラ、Aを入れたら中~強火で炒め混ぜ、水分がなくなり具材全体にタレが絡んできたら出来上がり。
*お好みでゴマをまぶして下さい。

鮭にはタンパク質の他に、ビタミンB6やビタミンD、DHA、EPAなどが豊富に含まれています。
とくに、ビタミンB6は摂取したタンパク質を代謝して体内で利用する際に必須の栄養素となるため、一つの食材で同時に摂取できる鮭は効率よくタンパク質を使う上で理にかなった食材となります。
秋の根菜と一緒に、美味しく、バランスよく食卓に取り入れてみて下さい。