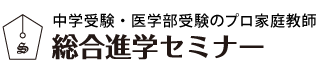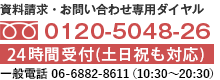前回は、食べた物をきちんと消化・吸収するためのポイントとして、主に「消化」にスポットを当てて、タンパク質の重要性についてご紹介しました。
今回は、それら消化されたものをうまく「吸収」するためのポイントや栄養についてご紹介します。
食べた物を吸収する主役となるのが、腸です。
つまり、この腸の状態により吸収の能力には大きな差が出るため、腸内環境と腸自身の健康に気をつける事が重要になります。
最近では、腸活という言葉もよく聞くようになり腸の重要性が広く知られてきましたが、腸の状態もまた食べた物によって左右されます。

◉腸の働き
腸は食べた物の栄養を吸収する器官として重要な働きをしますが、その他にもさまざま な役割を担っています。
◆ホルモンの生成……腸内では消化に関するホルモンや、食後血糖値の急上昇を抑えるインクレチン、精神を安定させるセロトニンなどが作られています。
◆ビタミンの生成……腸内細菌にはビタミンB群や、ビタミンKなどを生成する働きもあり、私たちの健康維持に大きく関わっています。
◆バリア機能……腸は必要な栄養素などを吸収する反面、細菌などの有害物質は体内に吸 収することなく排除する、選択的バリア機能を備えています。
◆免疫の要……体内に入った病原体と戦う免疫細胞の約7割は腸に生息しており、それら の機能は腸内環境によって影響を受けます。
このように多くの働きを担っていることから、腸の状態がその人自身の健康状態と大きく結びついていることが分かります。
◉腸内環境
人の腸内には100兆個ともいわれるほど膨大な数の腸内細菌が棲んでいます。
この腸内細菌は大きく分けて、善玉菌、悪玉菌、日和見菌(腸内環境によって善玉菌のような働きも、悪玉菌のような働きもする細菌)の3種類に分けることが出来、それらの菌のパワーバランスによって腸内環境の良し悪しが決まってきます。
健康な人の腸内では、菌の比率は『善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7』という割合で、善玉菌が悪玉菌を抑える形で一定のバランスが維持されています。
この腸内環境はストレスや不規則な生活、偏った食事などによって崩れやすくなり、特に食事においては、悪玉菌のエサとなる砂糖や人工甘味料の摂取が多くなると悪玉菌優位の環境が出来やすくなります。
また、食品添加物は腸内環境のバランスを乱し、腸管粘膜のバリアを破壊することもあります。
その結果下痢や便秘、腹部膨満感、肌荒れ、メンタルの不調などが起こるばかりか、腸の大きな働きの一つであるバリア機能や免疫力も低下し大事な場面で体調を崩しやすくなってしまいます。
反対に、善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖などを含む食物を多く摂取したり、善玉菌を多く含む発酵食品を摂取したりすることで、善玉菌優位の環境が作られやすくなります。
腸内環境を整えることは、すなわち善玉菌優位の環境を維持していくことであり、それには食事が重要となってくるのです。
◎善玉菌を元気にする食べ物……食物繊維、オリゴ糖、発酵食品
◎避けたい食べ物……砂糖、人工甘味料、食品添加物
長時間の勉強によるストレスや運動不足、不規則な生活リズムなどに陥りやすい受験生においては、特に食事面での腸内環境への配慮は欠かせません。
<レシピ>
~わかめと新玉ねぎの腸活サラダ~
【材料】(4人分)
- ・乾燥わかめ……4g
- ・新玉ねぎ……1/2個
- ・えのき……1/2株(100g)
- ・ささみ……1本
- ・きゅうり……1本
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・すりごま……大さじ1
- ・しょうゆ……大さじ1
- ・酢……大さじ1
- ・砂糖……大さじ1
- ・オイスターソース……小さじ1/2
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・塩……少々

【作り方】
- ① 乾燥わかめは水で戻したあと、しっかりと水気をきっておく。
新玉ねぎは薄くスライスし、広げて30分以上置いて、水で洗いよく水気をきっておく。
えのきは石づきを切り落とし、食べやすい長さに切り耐熱ボウルにいれてラップをしたら、電子レンジ600Wで2分30秒加熱する。
ささみは、沸騰したお湯に入れて30秒程したら、火を止め20分程おき、食べやすい大きさに手でさく。
きゅうりはスライスして、塩を一つまみ(分量外)まぶし数分置いて出てきた水分を絞る。 - ② ボウルにAと①の食材全てを加えよく混ぜ合わせ、最後に塩で味を調えたら出来上がり。

わかめなどの海藻類には水溶性食物繊維(便をやわらかくしたり、血糖値の上昇を抑える)が多く含まれており、えのきなどのきのこ類には水溶性だけでなく不溶性食物繊維(便のかさ増しをしたり、腸の動きを活発にする)も豊富です。
また、この時期柔らかく甘い新物が出回る玉ねぎには善玉菌のエサとなる食物繊維の他にオリゴ糖も豊富に含まれており、さっぱりとした酢の物やサラダにすることで沢山摂取できます。
◉腸の健康を守る
グルテンフリー・カゼインフリー
グルテンフリー・カゼインフリーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
実際にこれらに気を付けた食生活をされている方もいるかもしれません。
そもそも、グルテンとは小麦に含まれているタンパク質の一種であり、カゼインは乳製品に含まれているタンパク質になります。
これらは、人の腸内に残りやすく消化しきることが出来ない物質であるため、未消化物として腸に溜まり、そこから炎症を起こし腸のバリア機能を破綻させてしまいます。
その結果、通常であれば腸内に留まり排除されるような有害物質が、腸管から血液中へと入り込みさまざまな疾患や不調を引き起こします。
お腹がよく張る、下痢をしがち、皮膚トラブルが多い、疲労感が強いなど一見すると普段の生活からくる何気ない不調も、実は腸のトラブルが原因ということもあります。
症状には個人差がありますが腸の健康を守る上で、特に普段から小麦製品や乳製品を多く摂っている人は一度食生活を見直してみることが必要です。
グルタミン(腸のエネルギー)
タンパク質を構成するアミノ酸の一種であるグルタミンは、腸内の粘膜にある絨毛(小腸内面の粘膜に絨毯のように張り巡らされた細かい突起)のエネルギー源となります。
食べた物の栄養は腸管の絨毛から取り入れられ、反対に細菌やウィルスなどの有害物質は絨毛のバリア機能により排除されます。
そのため、この腸の絨毛を常に元気に保つことが腸自体の健康を守る上でも重要となり、それに欠かせないのがグルタミンです。
先述したように、グルタミンはアミノ酸であるため食品ではタンパク質に多く含まれます。
毎食ごとにタンパク質をしっかり摂ることが、腸の健康を守り、食べた物をしっかりと吸収する上でも重要になってくるのです。
<レシピ>
~根菜と鶏肉の甘酢和え~
【材料】(4人分)
- ・ごぼう……1/2本
- ・れんこん……100g
- ・鶏もも肉……300g
- ・豆苗……60g(1/2袋)
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・酒……大さじ1
- ・しょうゆ……大さじ2
- ・みりん……大さじ2
- ・砂糖……大さじ2
- ・酢……大さじ1
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・すりごま……大さじ2

【作り方】
- ① ごぼうは皮をこそげ落とし斜め切りにする。
れんこんは皮をむき5㎜幅に切る。
鶏もも肉は食べやすい大きさに切り、豆苗も洗って食べやすい長さに切る。 - ② ごぼう、れんこん、鶏もも肉に片栗粉を薄くまぶしたら、多めの油で揚げ焼きにし一旦取り出す。
- ③ フライパンに残った油をキッチンペーパーでふき取ったら、Aを入れて沸騰したら➁のごぼう、れんこん、鶏もも肉を戻して、豆苗も加えて炒める。
- ④ 全体にタレが絡み豆苗がしんなりしてきたら、すりごまを加えよく混ぜ合わせたら出来上がり。

ごぼうやれんこんなどの根菜に多く含まれている不溶性食物繊維は、善玉菌を増やして腸内環境を整えるだけでなく、体内で水分を吸収して膨張するため腹持ちが良く食べ過ぎを防ぐこともできます。
また、これに合わせた鶏もも肉は、腸のエネルギー源となるグルタミン(タンパク質)を豊富に含んでおり、ビタミンB群に富んだ豆苗との食べ合わせもおすすめです。冷めても美味しい一品ですので、ぜひ一度作ってみて下さい。