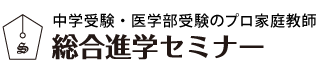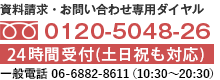受験生において夏は、よりいっそう勉強に集中しまとまった時間を確保できる重要な時期です。
しかし、猛暑日が激増している昨今の夏は残暑も厳しく長いものとなり、例年以上に身体が気温についていけず食欲がなくなり、しんどく感じると共に、心も夏バテにかかってしまいだるい、やる気が起きないといった場面も増えているかもしれません。
そもそも、体も心も食べた物でできているため、食欲不振からの栄養不足や食事の偏りは心身ともに悪循環を生みだします。
暑い夏だからこそ水分はもとより、食事においてもしっかりと摂りたい栄養素を意識しつつ、食材選択や調理の工夫をしていくことが重要です。

◎夏こそ摂りたい栄養素
◆タンパク質
タンパク質はすべての細胞の主材料となっており、心を作る神経伝達物質(ホルモンなど)の材料でもあります。
意欲や学習能力に関わるドーパミン、心を落ち着かせ安定させるセロトニンなどの神経伝達物質もタンパク質を主材料として作られます。
一方で、夏の暑さで食欲が低下すると、食事は冷たく食べやすい糖質に偏りがちになり、タンパク質の摂取は減少する傾向にあります。
そのため、夏場のタンパク質不足は、受験生にとっては集中力の低下や落ち着かない、だるいといった精神面にも大きな影響を与えます。
タンパク質は食べ溜めできない栄養素でもあるため、毎食しっかり摂るのもポイントとなります。
肉や魚などを毎食たくさん食べられなくても、副菜や汁物に少しずつ取り入れる工夫や補食などでもタンパク質を補う意識をすることで、無理なく続けていくことが重要です。
◆鉄分
鉄分もまた神経伝達物質の生成過程で必要となる栄養素であり、肉などのタンパク質食材に多く含まれています。
体に入った鉄はタンパク質と結びつき体内を巡るため、タンパク質不足は鉄や鉄を運ぶためのトランスフェリンなどの不足にも繋がりやすく、子どもや女性では隠れ貧血の原因にもなります。
また、鉄分は汗と一緒に流れ出てしまう成分の一つであり、夏場に失われやすいためこの時期は貧血にとくに注意が必要です。
夏バテと貧血は症状が似ているため、夏バテかも?と思っていても実は夏場の貧血からくる不調ということもあるため、しっかり摂取することを意識する必要があります。
◆ビタミンC
夏場は強い紫外線や暑さ、それらによる睡眠不足や食欲不振など、多くのストレスにさらされやすい時期です。
体はストレスがかかると、抗ストレスホルモンを合成・分泌し対抗しており、ビタミンCはそのホルモン合成に必要な栄養素となります。
そのため夏はビタミンCの消費量が増え、体内では不足しやすい状態となります。
ビタミンCが不足し抗ストレスホルモンの合成が減少すると、食欲減退や疲労感が強くなり、免疫機能も落ちてきます。
そのため、夏場は特にビタミンCの摂取を意識することが重要になってきます。
また、抗ストレスホルモンは副腎で作られるため、糖質をよく摂取する人においては、慢性的に副腎が過剰に働き疲れており、十分な抗ストレスホルモンの合成・分泌が出来ない状態となるため、糖質の摂り方にも注意が必要です。
◎夏に摂りたい食材
東洋医学において夏は熱や湿気が体内に入りやすく、汗を多くかき過ぎることで気(エネルギー)や体液を損ないやすいとされています。
これらが夏バテなどの不調に繋がるため、この時期に適した食物を摂ることで体を整えることが勧められており、今回はその中でも夏を乗りきる為の特性をもつ食材を紹介します。
◇水分代謝を上げる食材……夏は利尿作用のある食材を摂取することで、体内の熱を冷 まし水分代謝も上がるとされています。
食材:きゅうり、ゴーヤ、なす、スイカ、ズッキーニ など
◇滋養強壮、疲労回復に優れた食材……夏は一年のうちで最も活動的になる分、体力の消耗も激しく疲れやすくなります。そのため、体力や気を補い巡らせる食材を取り入れる事が重要です。
食材:ウナギ、豚肉、山芋、高麗人参 など
◇体を温める食材……冷たい物の摂取や冷房の効いた部屋にいることも多いため、夏は冷えによる胃腸の消化吸収機能の低下も見られやすくなります。そのため、夏こそ体を中から温める食材の摂取がおすすめです。
食材:しょうが、にんにく、ねぎ、大葉、みょうが など
◆注意したい食材……糖分(スイーツなどの甘味)の多い物は水分代謝を妨げ、体内の巡りを妨げてしまうため、夏場に多く摂取するのは控えましょう。
<レシピ>
~豚肉と夏野菜の焼き浸し~
【材料】(4人分)
- ・豚バラ肉(薄切り)…150g
- ・なす……1本
- ・しし唐……4本
- ・オクラ……4本
- ・ズッキーニ……1/2本
- ・大葉……適量
- ・水……200ml
- ・かつお節……5g
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・しょうゆ……大さじ1
- ・みりん……大さじ1
- ・酒……大さじ1
- ・砂糖……小さじ2
- ▲▲▲ A ▲▲▲

【作り方】
- ① 豚バラ肉は食べやすい長さに切り軽く塩(分量外)をふる。
なすはへたを切り落とし縦に4等分に切り、皮目に斜めに浅く切り込みを入れる。
しし唐は半分に切る。
オクラは縦半分に切り、ズッキーニは5㎜程の半月切りにする。
大葉は千切りにする。 - ② フライパンで豚バラ肉を、軽く焼き目がつくまで焼く。
豚バラ肉を取り出し、残った油にさらに大さじ3程の油(分量外)を足して、野菜を全て入れ焼き色がつくまで揚げ焼きにする。 - ③ 焼いた豚肉と野菜を耐熱の皿やバットに入れる。
- ④ 小鍋に水を沸騰させ、かつお節を加えたら火を止めて、2分程置きザルなどでかつお節をこす。
残った出汁にAを加えてひと煮たちさせる。 - ➄ 出汁が熱いうちに③に注ぎ粗熱がとれたら冷蔵庫で1日ほど置いて出来上がり。
*食べる際には、常温に戻して(レンジなどで軽く温めてもOK)召し上がって下さい。

疲労回復に優れた豚肉と、水分代謝を上げる夏野菜を組み合わせ、暑い夏でもさっぱり食べられる焼き浸しにしました。
夏場は暑いからといって、冷たい物ばかり口にすると胃腸が冷えて消化機能が低下してしまうことも多いため、茹でる、蒸す、焼くなどして消化しやすく、常温でも食べやすく調理した物の摂取もおすすめです。
◎バテない体は良質の睡眠から!!
最近の夏は、夜間も冷房をつけなければ寝ることが出来ないような日が続くようになりました。
そのため、夜中に部屋が冷えすぎて起きてしまうことや、反対に設定温度の調節が難しく暑くて起きてしまうなど、熟睡できないと感じる方も多いのではないでしょうか。
加えて、食欲がないからと夕食を冷たいものや、簡単なもので済ませようとすると、食事バランスが崩れさらに睡眠の質が落ちてしまいます。
寝苦しい夜でも、しっかり次の日にむけてよい睡眠がとれるように食事からのアプローチを考えてみましょう。
◇睡眠の質を高める食事のポイント
寝る直前に食事を摂ると、寝ている間に食べた物を消化・吸収するために体は休むことなく働かなくてはならず、睡眠の質が落ちてしまいます。
食べた物を消化するのにかかる時間は、食材にもよりますが少なくとも2~3時間はかかるため、夕食などのまとまった食事も就寝時間の2~3時間前には済ませておきたいです。
塾で帰宅が遅くなる場合は、塾前や途中にできるだけまとまった食事を済ませるのがおすすめです。
夕食に多くの糖質を摂取すると、就寝中に血糖値が急激に上がり、その後下がるといった乱高下が起こります。
その結果、体は血糖値を一定にするために奔走しなくてはいけないため、体を休めることに集中できません。
一方で、就寝中は細胞や組織の新陳代謝が促進される時間帯でもあるため、その材料となるタンパク質を十分に体に満たしておく必要があります。
そのため、夕食はタンパク質を意識し、糖質を適量にとどめるバランスが重要になってきます。
就寝前に空腹を我慢して寝ると就寝中に血糖が下がり、下がった血糖値を上げようと神経や臓器が頑張って働くため、体はゆっくり休むことが出来ず睡眠の質が落ちてしまいます。
そのため、寝る前にお腹がすいたら我慢せずに消化しやすく、かつ就寝中に血糖値の乱高下がおきないタンパク質を中心に適量摂取することがおすすめです。
半熟ゆで卵、ホットミルク(豆乳)、豆腐、白身魚、サラダチキン、プロテイン など
<レシピ>
~簡単夜食にも!焼き卵豆腐~
【材料】(4人分)
- ・絹ごし豆腐…150g
- ・卵……2個
- ・しょうゆ……大さじ2/3
- ・みりん……大さじ2/3
- ・白だし……小さじ1
- (とうもろこしあん)
- ▼▼▼ A ▼▼▼
- ・白だし……大さじ1
- ・水……200ml
- ・とうもろこし……1/3本
- ▲▲▲ A ▲▲▲
- ・水溶き片栗粉……大さじ1

【作り方】
- ① ボウルに絹ごし豆腐を入れてハンドミキサー(なければ泡だて器)などで滑らかになるまで攪拌する。
- ② そこに卵と、しょうゆ、みりん、白だしを加えてよく混ぜ合わせ、小さめの耐熱容器に注ぎトースターで10分程焼き、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。
- ③ 包丁でとうもろこしの実を芯から削る。小鍋にAを入れ沸騰したら火を止めて、水溶き片栗粉でとろみをつけ、冷蔵庫で冷やしておく。
- ④ 食べる前に➁の卵豆腐にとうもろこしあんをかけたら出来上がり。

消化のよいタンパク質である豆腐と卵を使い、上のあんには夏に旬をむかえるとうもろこしを入れ甘さと食感を加え、冷やすことで夏でも食べやすく、食欲のない時にもおすすめの一品にしました。
混ぜて焼くだけの簡単調理なので、作り置きや夜食などにも是非一度作ってみて下さい。